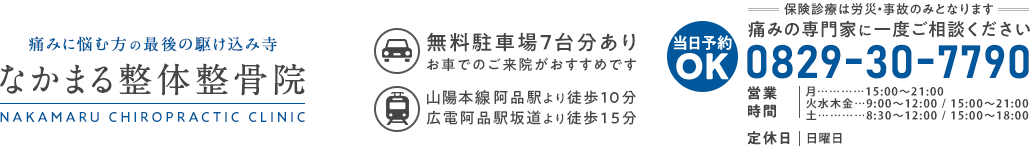query_builder2025.07.24
リアルのメタトロンさくら4D分析測定を経験伝統医学で相互補完します。
① 【包括的な原因分析】
② 【メタトロンさくらの使用改善アプローチ】
🌀1)エネルギー調整(周波数バランス補正)
🌊2)感情開放と潜在意識へのアプローチ
🥦3)食材相性・内臓サポート
🧠4)身体構造との統合分析(痛み・筋膜・トリガーポイント)⏳5)生活習慣からの調律提案(6つのリズム)
※6つのリズム
食(体質・消化・栄養吸収サポート)動(筋肉・動き・エネルギー循環)休(睡眠・休息・自律神経)心(感情・メンタルケア)環(環境・外部ストレス)気(エネルギーフィールド・波動場)
③ 【未来の傾向・未病予測】
④ 【身体・感情・魂の統合を促す“キーワード整理”】
⑤ 【栄養・食事・レメディの具体提案】
🎁《得られるベネフィット》
- 🧠 西洋医学では説明しきれない“根本的な要因”を可視化
- 📊 データに基づく多角的なアプローチで納得感あるセルフケアが可能
- 🌿 体・感情・魂のレベルにわたる包括的な調整方針が明確に
- 🌀 未病の段階で変化を察知し、予防的な改善アクションを実践できる
- 💫 「ただ治す」ではなく、「本来の自分に戻る」ための道しるべとなる
※「ホームページのシートBを読みました!」
と、lineでお伝えくださらないと、ここまでのアプローチは、致しませんよ!
query_builder2025.07.13
🌀その“ズレた体質診断”、信じすぎていませんか?〜あなたに本当に必要なのは、”本来の声”を聴くこと〜
「前にメタトロンを受けたけど、ピンとこなかった…」
「体質って言われたけど、逆に混乱した…」
そんな声、実は少なくありません。
なぜなら、多くのサロンや治療院では
🌍ロシアで作られたメタトロンの結果を、そのまま伝えているだけ。
でもそれって…
✔ 日本人の体や心、感覚とはちょっとズレていたり
✔ 「一時的な症状」を「体質」と勘違いしてしまったり
実は、間違った方向に進んでしまうこともあるんです。
💎じゃあ、どう違うの?
当院のメタトロンは “読み解き方” がまったく違います。
🌿「いま」の症状だけじゃなく、
🌱「本来のあなたのバランス」を探る“共鳴メタトロン”へ。
👩⚕️国家資格を持つ「主治中医師」が
🌌メタトロンの波動データに
🌞東洋医学の叡智(陰陽五行・氣・暮らしのリズム)をかけあわせて
✅ 「あなたの本当の体質」
✅ 「心と体、魂がズレている場所」
✅ 「どう整えれば、もっと楽になれるか」
を丁寧に導き出します。
🍀あなたの中には、ちゃんと整う力があります。
不調は、あなたが悪いんじゃない。
ちょっとだけ、リズムがずれてしまっているだけなんです。
🌈それを“やさしく共鳴”で整えていくのが、
当院の《共鳴メタトロンセッション》です。
✨まずは、あなた自身の声を聴いてみませんか?
🔹【プログラム①】主治中医師 × 波動分析 × 東洋の知恵サポート
🔸【プログラム②】五行体質診断チェックリスト(まずはここから)
query_builder2025.05.31
🌸メタトロンさくらの仕組み(素粒子の視点から)
• 私たちの体は、細胞よりもっと小さな「素粒子(そりゅうし)」でできていて、すべてのものが**波(エネルギーの振動)**を出しています。
• 元気なときの体は、素粒子の波が整っていて、バランスのとれた「きれいなリズム」をしています。
• でも、ストレスや疲れ、病気があると、その波のリズムが乱れてしまうことがあります。
• 「メタトロンさくら」は、頭にイヤホンのようなものをつけて、体のさまざまな場所が出している波動を読み取り、コンピューターで表示します。
• どこの波が乱れているかを見ることで、体の不調や乱れのサインを早く見つけることができます。
• さらに、乱れた波に対して「理想的な波」を当てて、自然に体が元の状態へ戻るようにサポートしてくれます。
🌱つまり、「メタトロンさくら」は、
私たちの体のエネルギーのリズム(波動)を調べて、ととのえる、エネルギーの健康チェック機器なのです。
⸻
🌟メタトロンさくらで【わかること】
1. 体のどこが弱っているか
→ エネルギーの波が乱れている場所が画面に表示される
(例:胃が疲れてる、腰の波動が低下してる、など)
2. 体のバランス状態
→ 自律神経・内臓・骨・脳・感情などの全体のバランスが色や数値で見える
3. 不調の原因のヒント
→ 波動の乱れから、「生活習慣」「食べ物」「ストレス」などの影響が読み取れる
4. エネルギーの相性
→ 食べ物・植物・音楽・アロマなどとの「共鳴度(相性)」もチェックできる
⸻
🌱メタトロンさくらで【できること】
1. 波動調整(メタセラピー)
→ 乱れた波に「本来の正しい波」を当てて、体の回復をサポート
2. 体質・心の傾向を知る
→ 潜在的なストレス・感情ブロック・体質傾向なども見つけやすくなる
3. 未病(病気になる前の乱れ)に気づける
→ 病気になる前に、波動の乱れで予兆をつかめる可能性がある
4. セルフケアのヒントがもらえる
→ 今の自分に合った食事・運動・休養・アロマ・音・自然療法などのアドバイスが得られる
🌀つまり:
メタトロンさくらは、体や心の「エネルギーのゆがみ」を見つけて、自然なバランスを取り戻すサポートをしてくれるツールなのです。
🔍【比較:メタトロンさくらのメタセラピー vs. 氣功・エネルギー療法】
観点
①メタトロンさくら(メタセラピー)
氣功・エネルギー療法
原理・理論
量子波動理論(非線形システム解析)、生体共鳴、フーリエ変換など科学ベースの解析技術測定方法
ヘッドセットを用いた周波数測定(器官・細胞・感情など)→波動状態を数値や色で可視化
施術方法
メタセラピー(周波数調整)による情報転写・自己調整力の促進
対象領域
臓器・組織・感情・食品との相性・病因候補の可視化と修正
客観性
結果は数値・画像・チャートで表示、ビフォーアフター比較可能
施術者の能力差
装置主導のため、施術者による差がない
施術の安定性・再現性
高い(設定とプロトコルによる標準化可能)
②氣功・エネルギー療法
原理・理論
東洋医学・気の流れ・チャクラ・経絡など、経験則と伝統的直感による理論
施術者の感覚や手の感知力による「氣」の状態把握
施術方法
手かざし、呼吸法、気の流れの調整、意識集中など
対象領域
主に気の滞り・ストレス・エネルギーの乱れ
客観性
施術効果は主観的(施術者と受け手の体感に依存)
施術者の能力差
施術者の経験・気感・技術によって大きく異なる
施術の安定性・再現性
個人の状態・施術者のコンディションに左右されやすい
✅【メタトロンさくら・メタセラピーが優れている点】
① 可視化できる(波動状態が数値・色・グラフで見える)
• 感覚的な「なんとなく良くなった」ではなく、施術前後の変化を明確に比較できる
• 「赤→黄→緑」と色で変化が分かることで、納得感・安心感が高い
② 原因の仮説が立てやすい(器官・感情・食品レベルまで)
• 「胃の負担が強く出ている」「小腸がストレス反応を示している」など、臓器別に反応がわかる
• 「怒り」「恐れ」などの感情的ストレスも分析でき、心理面のアプローチにもつながる
• 食品や身につけるものとの相性も調整可能(例:サプリ、歯の詰め物、電磁波など)
③ 施術のブレが少ない・安定した施術が可能
• 人の氣感や体力に依存せず、誰が扱っても一定の結果が期待できる
• セラピーは装置による共鳴・修正波の送信で行われ、施術者の疲労や主観が入りにくい
④ 再現性・検証性が高い
• 同じ設定であれば、他の人でも同じような波動状態を確認・共有できる
• 体調変化と波動変化を日常記録と紐づけて分析できる
⑤ 安心・安全・副作用なし
• 周波数調整による「情報の書き換え」であり、薬剤や機械的刺激がない
• 高齢者や子どもでも安心して使える(氣功における“当たり過ぎ”のリスクなし)
🧘♀️【まとめ
ポイント
メタトロンさくらはこんな方におすすめ
✅ データを重視する方
客観的な数値・グラフで安心感が欲しい人
✅ 理論に基づいて整えたい方
エネルギー的な不調を科学と感覚の融合で理解したい人
✅ 日常の生活改善にもつなげたい方
食事・環境・感情ストレスを可視化し、セルフケアに活かしたい人
✅ 氣功やエネルギー療法で効果が安定しなかった方
再現性ある施術で「体感+結果の裏付け」を求める人
query_builder2025.05.29
【ご予約に関する大切なお知らせ】
いつも当院をご利用いただきありがとうございます。
皆さまにとってより良い施術環境を保つため、ご予約の取り扱いについて再度ご案内させていただきます。
最近、一部の方において度重なる予約変更・キャンセルが見受けられ、他のご予約希望の方のご案内が難しくなるなど、運営上の支障が出ております。
特に、
✅ 直前での変更・キャンセルが複数回続く場合
✅ 同じ時間帯の枠を何度も押さえ直すような形になる場合
は、1人で2枠を占有してしまうような状態となり、大変ご迷惑となります。
当院では、以下の通りご予約制度と料金を設けております:
🔷 通院の基本料金
・月1回の方:6,600円(税込)
・月2回以上通院できる方:割引料金 5,500円(税込)
🔶 都度予約で確定できない場合
・確実に来られない場合、その都度予約として都度料金6,600円を適用させていただきます。
・変更が多い方には、原則「確実に来られる日」のみのご予約をお願いしております。
例えば、「金曜日は仕事の都合で変更になるかもしれない」という場合は、
お休みの日など変更がない日にご予約いただく方が確実です。
「面倒だから」という理由で毎回直前の変更をされると、
他の患者さまにもご迷惑がかかり、当院の運営にも影響が出てしまいます。
当院は一人ひとりにしっかりと向き合いたいと考え、時間を確保してお迎えしています。
今後も安心してご利用いただける場を守るためにも、皆さまのご理解とご協力を心よりお願い申し上げます。
ご不明点がある場合は、いつでもお気軽にご相談ください。
query_builder2024.08.07
なかまる整体整骨院利用規約
セルフ利用機械第1条(目的) 本規約は、当院内のセルフ利用機械(以下「機械」といいます)の適正な利用を促進し、全ての利用者が快適に利用できるようにすることを目的とします。
第2条(利用の申し込み)
- 機械の利用は、当院の受付にて事前に申し込みを行うものとします。
- 申し込みの際には、利用者の氏名、連絡先、および利用予定時間を登録していただきます。
第3条(利用時間)
- 機械の利用時間は1回につき30分以内とし、1日に1回までとします。
- 利用時間の延長を希望する場合は、他の利用者の予約状況を確認の上、受付にて手続きを行ってください。
第4条(利用方法)
- 機械の利用前に、必ず使用方法を確認し、正しく使用してください。
- 使用後は、必ず機械の電源をオフにし、周囲を清掃してから次の利用者に譲ること。
- 機械表面や接触部分を消毒用シートで拭き取ってください。
- 足元や椅子など、使用中に触れた部分も清掃してください。
- ゴミや使用済みのシートは、指定のゴミ箱に捨ててください。
- 機械の使用中に異常を感じた場合は、直ちに利用を中止し、受付に報告してください。
第5条(利用の制限)
- 以下のいずれかに該当する場合、機械の利用をお断りすることがあります。
- 健康状態が優れない場合
- 利用方法を守らない場合
- 他の利用者に迷惑をかける行為を行った場合
- その他、当院が不適切と判断した場合
第6条(利用者の義務)
- 利用者は、機械を丁寧に扱い、破損や汚損をしないように努めるものとします。
- 機械や設備を故意または過失により破損した場合、修理費用を負担していただく場合があります。
第7条(安全管理)
- 利用者は、自己の責任において機械を利用するものとし、利用中の事故や怪我については、当院は一切の責任を負いません。
- 機械の利用に際しては、適切な服装で利用し、安全に留意してください。
第8条(個人情報の取扱い)
- 当院は、利用者の個人情報を適切に管理し、無断で第三者に提供することはありません。
- 利用者の同意を得た場合や法令に基づく場合を除き、個人情報を第三者に提供することはありません。
第9条(規約の変更)
- 本規約の内容は、必要に応じて変更することがあります。
- 規約の変更は、当院のホームページまたは院内掲示にて告知します。
第10条(その他)
- 本規約に定めのない事項については、法令または一般的な商慣習に従うものとします。
- 本規約の解釈に疑義が生じた場合は、誠実に協議して解決するものとします。
付則 本規約は、2024年8月7日より施行します。
必要に応じて、細かい部分を調整したり、追加項目を設けたりすることも可能です。ご質問や追加の要望があればお知らせください。